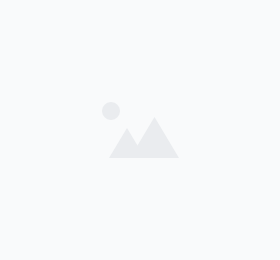NHK10分日本史「奈良時代」
NHKのサイトにある動画「10min.ボックス日本史」の第三回「進む中央集権化と国際文化(奈良時代)」を使った勉強法を紹介します。
コンパクトな動画ですが重要なポイントが詰まっています。
定期試験前の勉強などで活用してみてください。
この動画で学べること
この動画で対象としているのはタイトルにもある通り奈良時代。710年に平城京がつくられてから794年に平安京に遷都するまでを扱っています。
動画で取り扱っているのは下記のような内容です。
- 平城京の特徴
- 律令制度について
- この時代の仏教の役割、影響
- 天平文化について
奈良時代のポイントとなる政治、宗教(仏教)、文化について学べます。
この3つとも国際社会の影響を受けていることが特徴です。
この時代でキーとなる人物、聖武天皇や鑑真についても知ることができます。
まずは、動画を見てみましょう。
動画を見た後の確認問題
動画の内容を理解できているかの確認テストを作成しました。
【問.1】平城京がモデルとした都は?
(ア)隋の西安
(イ)唐の西安
(ウ)唐の長安
【問.2】律令国家の「律」と「令」はそれぞれ何を表わしているのか?
【問.3】次の出来事を古い順に並べなさい
(ア)鑑真の来日
(イ)唐招提寺の建立
(ウ)奈良の大仏完成の儀式
いずれも動画の中で説明されていることです。
(一応、ページの一番下に答えは掲載しています。)
動画では出てこない関連事項を整理
奈良時代に関しての関連トピックです。
ます、平城京と平安京のほかに藤原京と長岡京も整理して覚えておきましょう。
藤原京→平城京→長岡京→平安京の順番。
藤原京と平安京が現在の奈良県。長岡京と平安京が京都府にあたります。
奈良時代は国づくりが行われた時代でもあります。
国づくりでは政治体制だけでなく歴史書の編纂も行われました。
歴史書を編纂することで国家としての正当性を広めることが目的です。
古事記(712年)、日本書紀(720年)がつくられています。
この時代の文化(天平文化)は中国を経由して西アジアや南アジアの影響を受けていることも特徴です。そうしたものが多く納められているのが東大寺の正倉院です。
天平文化のキーワードとしては正倉院を覚えておきましょう。
確認問題の答え
【問.1】(ウ)唐の長安
【問.2】「律」…刑法、「令」…政治を行うためのきまり
【問.3】(ウ)奈良の大仏完成の儀式【752年】→(ア)鑑真の来日【753年】→(イ)唐招提寺の建立【759年】
間違えやすいポイント
奈良の大仏を作るために活躍したのは鑑真ではなく行基です。
二人とも漢字2文字で紛らわしいですが間違えないようにしましょう。