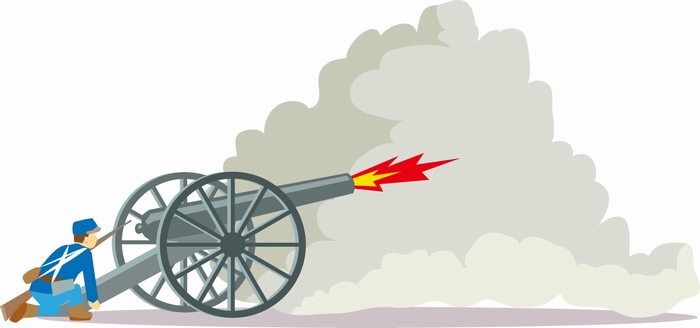中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

日本の歴史に出てくる改革一覧

中学歴史に出て来る「改革」といえば江戸時代の三大改革(享保の改革、寛政の改革、天保の改革)が思い浮かぶかもしれませんが、それだけではありません。
広い意味での改革とは、それまでの社会体制や経済問題などを解決するために実施された一連の動きのことを意味しています。このため用語としては「改革」とついていないものもあります。
ここではそうしたものも含めて一覧表形式にしました。
| 改革名 | 時代 | 主導者 | 目的・内容 |
|---|---|---|---|
| 大化の改新 | 飛鳥時代 | 中大兄皇子・中臣鎌足 | 班田収受法、公地公民制の導入 |
| 養老の改新 | 奈良時代 | 藤原不比等 | 律令体制の整備・強化 |
| 延喜・天暦の治 | 平安時代 | 醍醐天皇・村上天皇 | 政治の立て直し、貴族政治の安定 |
| 承久の改革 | 鎌倉時代 | 北条泰時 | 六波羅探題の設置、御成敗式目の制定 |
| 建武の新政 | 室町時代 | 後醍醐天皇 | 武家政権の否定、公家政権の復活 |
| 享保の改革 | 江戸時代 | 徳川吉宗 | 倹約令、新田開発、上げ米の制度 |
| 寛政の改革 | 江戸時代 | 松平定信 | 倹約令、寛政異学の禁、打ちこわし対策 |
| 天保の改革 | 江戸時代 | 水野忠邦 | 倹約令、株仲間解散、人返し令 |
| 明治維新 | 明治時代 | 明治政府 | 廃藩置県、地租改正、殖産興業 |
| 原敬内閣の政治 | 大正時代 | 原敬 | 地方分権、普通選挙法の準備 |
| 農地改革 | 昭和時代 | GHQ/日本政府 | 地主制度の解体、自作農の創設 |
| 財閥解体 | 昭和時代 | GHQ/日本政府 | 財閥の解体、経済の民主化 |
| 教育改革 | 昭和時代 | GHQ/日本政府 | 6-3-3-4制導入、教育の民主化 |
江戸時代の三大改革+田沼意次の政治
テスト対策としては、江戸時代の三大改革と田沼意次の政治が定番中の定番。詳細な一覧表がこちら。
| 改革名 | 実施時期 | 主導者 | 目的・内容 |
|---|---|---|---|
| 享保の改革 | 1716年 - 1745年 | 徳川吉宗 | 幕府の財政再建、倹約令の実施、新田開発の推奨など。 |
| 田沼の政治 | 1750年代 - 1770年代 | 田沼意次 | 商業の振興、財政の強化、町人の生活向上を目指す。 |
| 寛政の改革 | 1787年 - 1793年 | 松平定信 | 農村復興、倹約、備荒貯蓄の奨励、治安の回復など。 |
| 天保の改革 | 1841年 - 1843年 | 水野忠邦 | 財政再建、農村の復興、商業の規制など。 |
江戸時代の改革に共通しているのは、幕府のお金がなくなりそう(財政がきびしい)からなんとかしようというものです。そのための倹約したり、新しい収入源を開拓したりという流れ。
戦後日本の改革
GHQの主導により行われた第二次世界大戦後の改革も定期試験では定番です。
| 改革名 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 農地改革 | 地主が持っていた農地を政府が買い取り、小作人(農民)に安く売った。 | 自作農を増やし、農民の生活を安定させることで民主化を進めた。農村の経済格差が縮小。 |
| 教育改革 | 6・3・3・4制(小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年)を導入し、義務教育を小学校6年+中学校3年に拡大。 | すべての子どもに平等な教育の機会を与え、民主的な社会をつくる基礎を築いた。教育内容も民主主義を重視するものに。 |
| 財閥解体 | 三井・三菱・住友・安田などの大財閥を解体し、持ち株会社を禁止。 | 特定の大企業が経済を支配することを防ぎ、公正な競争を促進。日本経済の民主化を進めた。 |
世界の歴史に出てくる改革一覧
宗教改革(プロテスタント改革)
中学の歴史の授業で出てくる「改革」には宗教改革もあります。これは16世紀のヨーロッパで起こった出来事。それまでのカトリック教会が腐敗しているとして、新しい宗派プロテスタントが誕生しました。
宗教改革に関してはルターとカルバンを覚えておきましょう。
| マルティン・ルター | ドイツ | 「95か条の意見書」を発表し、カトリック教会の免罪符(罪の許しをお金で買う制度)を批判。聖書だけが信仰のよりどころだと主張 |
|---|---|---|
| ジャン・カルバン | スイス(*1) | 予定説(人が救われるかどうかは神があらかじめ決めている)を説き、厳しい信仰生活を重視。商工業者に受け入れれれる |
*1…カルバンが宗教改革を起こしたのがスイスで、カルバンの出身はフランスです。