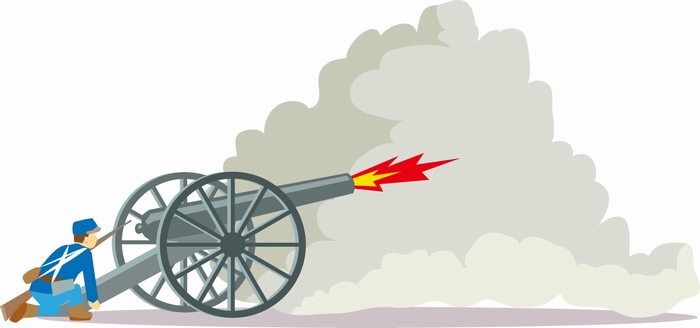中学歴史で出てくる条約一覧
中学の歴史で習う「ナントカ条約」についてまとめています。
条約というのは国と国とのあいだで結ばれたもののため、近代・現代史の分野で主に出てきます。紛らわしいものが多いので混乱しないように整理して覚えてください。
日本とアメリカのあいだの条約
まずは日本とアメリカのあいだの条約から。
ペリーの黒船来航により最初に結ばれたのが日米和親条約(1854年)。
これにより下田と函館の2港を開港することとなります。
その4年後に結ばれたのが日米修好通商条約(1858年)。
今度は函館、神奈川、長崎、新潟、神戸の5港が開かれることとなりました。
また、治外法権を認め、日本には関税自主権がない不平等条約でした。
これを強引に締結した井伊直弼は、のちに暗殺されることとなります。
もうひとつ日本とアメリカのあいだの条約で重要なのは、第二次世界大戦後に結ばれた日米安全保障条約(1951年)です。
これにより日本が独立後もアメリカ軍が国内に駐留することとなりました。
- 1854年 日米和親条約
- 1858年 日米修好通商条約
- 1951年 日米安全保障条約
日本とロシア(ソ連)のあいだの条約
日本とロシアとのあいだの条約で覚えておきたいものは3つ。
- 1875年…樺太・千島交換条約
- 1905年…ポーツマス条約
- 1941年…日ソ中立条約
樺太・千島交換条約は、ウルップ島以北の千島列島と日本領とし、樺太(カラフト)をロシア領としたものです。
ポーツマス条約は日露戦争の講和条約。
ポーツマスというのは日ロの仲介をしたアメリカの地名です。
日露戦争と日清戦争の講和条約
ポーツマス条約とセットで覚えておきたいのが下関条約。
- 日清戦争 → 下関条約(1895年)
- 日露戦争 → ポーツマス条約(1905年)
下関条約では日本は多額の賠償金を得ることが出来ましたが、ポーツマス条約では得られなかったため、国内で条約締結の反対運動が起こりました。
日本と中国のあいだの条約
下関条約が出てきたので、関連して覚えておきたいのが中国とのあいだの条約です。
- 1855年…天津条約
- 1895年…下関条約
- 1978年…日中平和友好条約
天津条約は清(中国)と結んだもので、朝鮮半島に出兵する場合は互いに事前通告するという内容のものです。
清(中国)関連では南京条約(1842年)というのも出てきますが、これはアヘン戦争後にイギリスと清のあいだで締結されたもので、日本は関係ありません。
南京条約は引っかけ問題の選択肢として出やすいので注意しておきましょう。