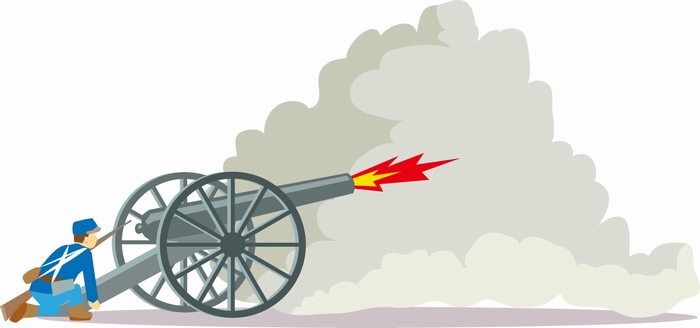中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

都立高入試社会対策:歴史上の出来事「太政大臣」
東京都立高校の社会(歴史分野)の入試問題の定番のひとつに同じテーマの歴史上の出来事を古い順に並び替えるというものがあります。この問題への対策ページを作成しました。
今回は太政大臣に関してです。
中学歴史で習う歴史上の人物も何人かが太政大臣になっています。
それぞれの人物の施策、エピソードなど整理して覚えておきましょう。
中学歴史で覚えておきたい太政大臣
下記はいずれもある太政大臣に関する説明です。
それぞれ誰のことを述べたものかと古い順に並べるとどうなるか考えてみてください。
太政大臣(A)
- 中国に対して日本国王を名乗った
- 倭寇と区別するために貿易では勘合と呼ばれる割札を用いた
太政大臣(B)
- 中国との貿易の拠点として大輪田泊の修築を行った
- 崇徳上皇と後白河天皇の争いでは後白河天皇側について勝利した
太政大臣(C)
- キリスト教を禁止した後も、貿易は奨励した
- 全国でバラバラだった枡の容量を統一した
太政大臣(D)
- 4人の娘を天皇の妃とすることで外戚として権力を握るようになった
- 「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」と詠んだ
太政大臣とは
明治時代に内閣制度ができて廃止されたので、今は太政大臣はいませんが、それまでは大臣の中のトップの役職でした。適任者がいる場合にだけ任命される名誉職的な意味もありました。
歴代の太政大臣を見ても、権力を握ったものが任命されています。中学歴史で習う人物として覚えておきたいのは、藤原道長、平清盛、足利義満、豊臣秀吉です。
上に掲載した(A)〜(D)はこの4人にあてはまります。
海外との貿易に対する施策など似ている点があるので要注意!
(こうしたことが高校入試では出題されがちです。)
正解
太政大臣(A)から(D)を年代別に並べ替えると次のようになります。
(D)藤原道長 → (B)平清盛 → (A)足利義満 → (C)豊臣秀吉
整理して覚えておきましょう。