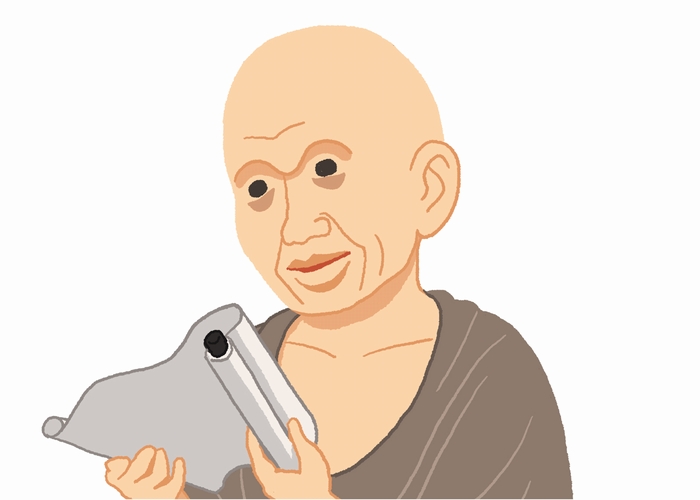中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

足利義満って何した人?
1338年に足利義満の祖父にあたる足利尊氏が京都に幕府を開きましたが、北朝と南朝にわかれている状態で内乱は続きました。
- 北朝…足利尊氏(京都)
- 南朝…後醍醐天皇(吉野)
南朝の勢力がおとろえてきたことで、北朝と合一させたのが室町幕府第三代将軍の足利義満です。義満は南北朝を合一させる前に京都の室町に花の御所とも呼ばれる邸宅を立て、ここで政治を行うようになっていました。
室町幕府と呼ばれるのようにったのは義満が室町に建てた邸宅(花の御所)で政治を行なっていたから。花の御所が描かれている作品として狩野永徳の洛中洛外図屏風も覚えておきましょう。
文化面では義満は観阿弥・世阿弥親子と保護し、猿楽・田楽を能として完成させました。
足利義満の関連年表
| 西暦 | 足利義満に関する出来事 | その他の出来事 |
|---|---|---|
| 1358年 | 誕生 | |
| 1368年 | 中国で元が滅び明がおこる | |
| 1369年 | 室町幕府第3代将軍となる | |
| 1378年 | のちに「花の御所」と呼ばれる場所に引越し | |
| 1392年 | 南北朝の合一 | 高麗が滅び李氏朝鮮がおこる |
| 1394年 | 太政大臣となる | |
| 1397年 | 金閣寺建立 | |
| 1404年 | 日明貿易が始まる | |
| 1408年 | 死去 |
征夷大将軍と太政大臣になった足利義満
武士として初めて太政大臣になったのは平清盛で、征夷大将軍で初めて太政大臣になったのが足利義満です。
足利義満の日明貿易と平清盛の日宋貿易
1368年に中国では元がほろび明がおこります。
この明と国交を開き貿易を始めたのが義満です。
明からは生糸、絹織物などが輸入され、日本からは銅や刀剣などが輸出されました。この日明貿易では勘合(かんごう)と呼ばれる札を使っていたことから勘合貿易とも呼ばれます。
日明貿易での利益は幕府の収入にとって大きなものとなりました。
足利義満は明に対して「日本国王」と名乗っていました。
中国との間の貿易では日宋貿易という言葉も出てきますが、これは平清盛が力を入れていたもの。中国は宋→元→明と変わっています。
足利義満の北山文化と足利義政の東山文化
足利義満は室町時代の文化にも影響を与えています(北山文化)。
比較されることの多い8代将軍の義政(東山文化)との違いをまとめました。
金閣寺のほうが足利義満です。
| 北山文化 | 東山文化 |
|---|---|
| 足利義満(3代将軍) | 足利義政(8代将軍) |
| 金閣寺 | 銀閣寺 |
| 観阿弥、世阿弥の能 | 雪舟の水墨画 |
足利義政のあとつぎ問題をめぐって細川氏と山名氏が対立したことから応仁の乱が始まります。
足利義満の年表確認問題
次の出来事を古い順に並べよ。
- (ア)金閣寺建立
- (イ)南北朝の合一
- (ウ)日明貿易が始まる
- (エ)足利義満が太政大臣となる
- (オ)足利義満が室町幕府第3代将軍となる
- (オ)足利義満が室町幕府第3代将軍となる(1369年)
- (イ)南北朝の合一(1392年)
- (エ)足利義満が太政大臣となる(1394年)
- (ア)金閣寺建立(1397年)
- (ウ)日明貿易が始まる(1404年)
将軍となってから南北朝の合一を行い、金閣寺を建立してから日明貿易を始めました。