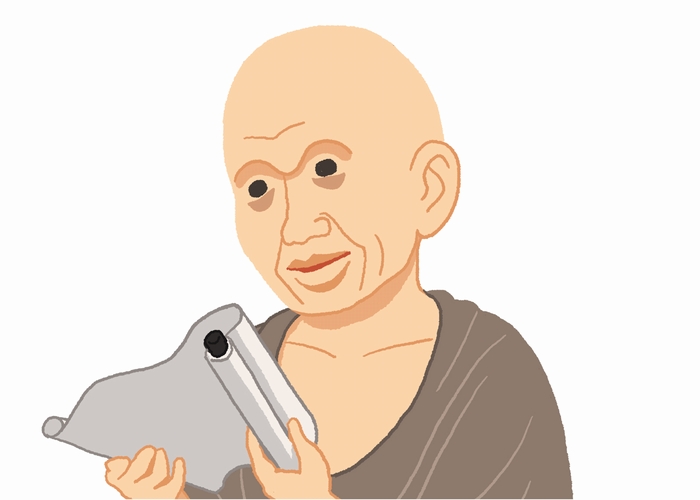卑弥呼(ひみこ)が政治面でしたこと
呪術を用いた国を治めた女性の王

卑弥呼(ひみこ)とは、3世紀の日本にあった邪馬台国という国の女王です。邪馬台国は、たくさんの小さな国が集まってできた連合国で、卑弥呼はその中でリーダーとなっていました。
卑弥呼は、霊的な力を使って国を治め、政治や戦争を導いたと考えられています。当時の人々は、卑弥呼が霊的な力を持っていると信じていたため、卑弥呼の言うことに服従していました。
卑弥呼の時代に邪馬台国では内乱があったとされていますが、「神のお告げ」を受けて卑弥呼がその内乱を収めたとされています。
卑弥呼は大勢の人々に自らの姿を見せることは少なく、弟が政治を補佐していました。また、千人もの侍女に囲まれて生活していたと言われています。
卑弥呼による「鬼道」と「骨占」
卑弥呼は占いの力を使って国を治めていました。このことは中国の歴史書『魏志倭人伝』にも、「鬼道」と呼ばれる呪術的な方法を用いて国を治めていたと記されています。
「鬼道」とは死者の霊や神霊と交信し、その言葉を民衆に伝えるような儀式だったと考えられています。
また、卑弥呼は「骨占」も行っていました。「骨占」とは、鹿の骨を焼いてその割れ方から吉凶を占う方法のことです。この占い方は中国で発祥し、北方のモンゴルやツングース族を経て日本にも伝わったものとされています。
卑弥呼はこうした儀式を宮殿で人に見られる行うことで神秘的な雰囲気も演出していました。
卑弥呼が外交面でしたこと
中国の歴史書に登場する卑弥呼

中国の「三国志」という歴史書によると、卑弥呼は239年に魏(当時の中国)に使者を送り、「親魏倭王(しんぎわおう)」の称号をもらいました。
この称号は魏から正式に外国の王として認められた証で、他国に対しても効果を発するものでした。
また、卑弥呼は、魏に貢ぎ物をして、その見返りとして、金印を受け取ったとされています。
卑弥呼は外交を巧みに利用することで、国内での権力を確かなものにしていきました。
魏志倭人伝の中の卑弥呼
魏志倭人伝には、当時の日本(倭)のようすがいろいろ書かれています。
当時の日本には文字がなかったので、日本の様子を知るための記録はほとんどありません。そのため、この魏志倭人伝を通して、卑弥呼や邪馬台国のこと、当時の人々の暮らしを知ることができるのです。
- 倭にはたくさんの国があって、その中でも一番力のあったのが邪馬台国。
- 女王の卑弥呼が国をまとめていた。
- 卑弥呼は人と直接会わず、妹や使者(つかいの人)を使って政治をしていた。
- 魏の国に使いを送り、「親魏倭王(しんぎわおう)」の称号をもらった。
- 村にはかべがなく、家は地面をほって住んでいた。
- 男も女も入れずみ(体に模様を入れる)をしていた。
- まじないや占い(うらない)を大切にしていた。
その後の日本に卑弥呼が与えた影響は?
卑弥呼がいた邪馬台国(やまたいこく)の場所は?

邪馬台国が日本のどこにあったかは現在でもわからず、九州説と畿内説の2つが有力とされています。
この邪馬台国がのちに大和朝廷になったとの説もありますが真偽は定かではありません。
卑弥呼の後継者問題
卑弥呼は247年頃に亡くなったとされています。
卑弥呼の死後、男性の王が即位しましたが国を治めることができませんでした。
その後、壱与(いよ)という女性が即位し国が安定したと記録に残っていますが、壱与がどのような統治を行ったのかについては、くわしくはわかっていません。
卑弥呼のために直径約150メートルの巨大な墓が築かれたとされていますが、その場所は現在でも特定されていません。