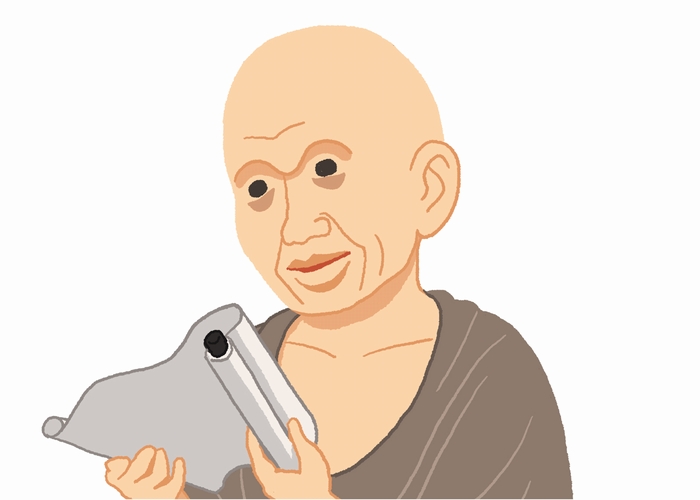中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

藤原道長(みちなが)って何した人?
自分の娘を天皇の后とすることで、天皇が幼いときは摂政として、成人してからは関白として政治の実権を握るのが摂関政治と呼ばれるものです。
最初に摂政や関白として権力を握ったのは、藤原良房(よしふさ)、基経(もとつね)親子。
しかし、基経が亡くなったあとは、摂政や関白を置かず菅原道真を重用する時代が続きました。
そこで、藤原氏が他氏排斥などにより権力を取り戻し、再び摂関政治の時代となったときに現れたのが藤原道長。摂関政治の全盛期を築いたのが藤原道長(とその子の藤原頼通)というわけです。
「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」
という道長が詠んだ歌は藤原氏の全盛期を表わしているものとして有名です。
藤原道長の関連年表
| 西暦 | 藤原道長に関する出来事 | その他の出来事 |
|---|---|---|
| 966年 | 誕生 | |
| 969年 | 安和の変(藤原氏による他氏排斥) | |
| 979年 | 宋が中国を統一 | |
| 11C頃 | 源氏物語(紫式部)、枕草子(清少納言) | |
| 1016年 | 摂政になる | 後一条天皇即位 |
| 1017年 | 太政大臣になる | |
| 1019年 | 出家 | 頼道が関白になる |
| 1027年 | 死去 |
道長が誕生したのは平将門の乱、藤原純友の乱のあと。
前九年の役(1051〜)、後三年の役(1083〜)は道長が亡くなってからの出来事です。
藤原道長が活躍した時代には源氏物語と枕草子も書かれました。
教科書などでは国風文化として取り扱われることが多いトピックなので覚えておきましょう。
藤原道長と親戚関係にある天皇
| 天皇 | 在位 | 関係 |
|---|---|---|
| 一条天皇 | 986〜1011年 | 藤原道長の義理の息子(娘の夫) |
| 後一条天皇 | 1016〜1036年 | 藤原道長の孫(娘の子) |
| 後朱雀天皇 | 1036〜1045年 | 藤原道長の孫(娘の子) |
| 後冷泉天皇 | 1045〜1068年 | 藤原道長の孫(娘の子) |
藤原道長は三代の天皇の外祖父(母方の祖父)となりますが、道長が生きていたときに天皇だったのは後一条天皇だけです。
国風文化がさかえた理由
菅原道真が遣唐使の廃止を進言したことで、日本独特の文化である国風文化が発達することとなりました。
源氏物語の作者である紫式部は藤原道長の娘である中宮彰子に仕えていました。
さらに、源氏物語に出てくる光源氏のモデルが藤原道長だという説もあります。
- 源氏物語…紫式部
- 枕草子…清少納言
国風文化についてはコチラのページにまとめています