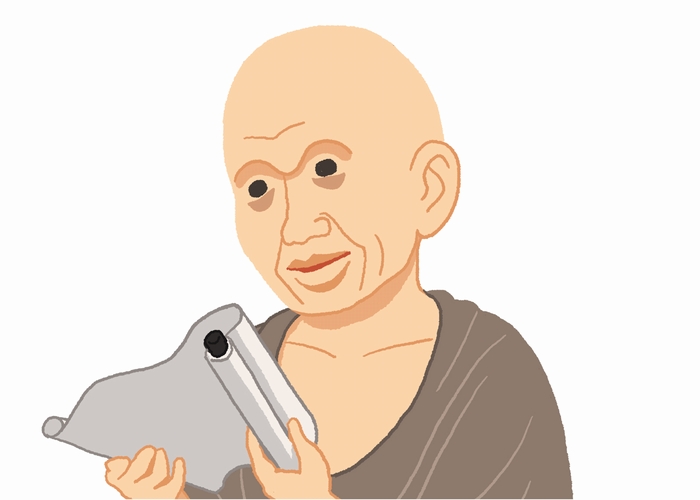中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

中学歴史に出る「天皇、上皇、法皇」
中学歴史に出てくる天皇、上皇、法皇の重要人物を一覧形式でまとめました。
天智天皇と天武天皇、後鳥羽上皇と後醍醐天皇などウロ覚えだとテストでどちらのことがわからなくなってしまいますよね。覚えやすいように表形式で整理しました。
天皇、上皇、法皇と頻出ポイント
| 天皇 | 読み | 属性 | 頻出ポイント | 関連人物 |
|---|---|---|---|---|
| 仁徳天皇 | にんとく | 大仙古墳が仁徳天皇陵と伝えられている | ||
| 雄略天皇 | ゆうりゃく | 倭の五王の武にあたるとされている | ||
| 推古天皇 | すいこ | 日本初の女性天皇 | 冠位十二階、十七条の憲法 | 聖徳太子 |
| 孝徳天皇 | こうとく | 中大兄皇子らが蘇我氏を滅ぼした後に即位 | ||
| 天智天皇 | てんじ | 中大兄皇子が即位 | 乙巳の変で蘇我氏を滅ぼす、庚午年籍(全国的な戸籍)を作成 | 藤原鎌足 |
| 天武天皇 | てんむ | 大海人皇子が即位 | 八色の姓を設ける、古事記、日本書紀の編纂を命じる | 大友皇子 |
| 持統天皇 | じとう | 天武天皇の妻 | 藤原京に遷都 | |
| 文武天皇 | もんむ | 妻の父が藤原不比等 | 大宝律令を制定 | 藤原不比等 |
| 元明天皇 | げんめい | 平城京に遷都(奈良時代の始まり) | ||
| 聖武天皇 | しょうむ | 妻の父が藤原不比等 | 仏教によって国を治めようと国分寺、国分尼寺、東大寺を建立 | 行基 |
| 孝謙天皇 | こうけん | 聖武天皇の娘 | 重祚して称徳(しょうとく)天皇となる | 道教 |
| 桓武天皇 | かんむ | 平安京に遷都、蝦夷と戦い東北地方を平定 | 坂上田村麻呂 | |
|
(摂関政治) |
||||
| 醍醐天皇 | だいご | 紀貫之らに古今和歌集の編纂を命じる | 菅原道真 | |
| 後三条天皇 | ごさんじょう | 摂関政治から天皇中心の政治へ | ||
| 白河天皇 | しらかわ | 上皇、法皇として政治の実権を握る(院政) | ||
| 後白河天皇 | ごしらかわ | 保元の乱で崇徳上皇に勝利 | 平清盛、源義朝 | |
|
(平氏、源氏政権) |
||||
| 後鳥羽上皇 | ごとば | 承久の乱を起こすも北条氏に敗れ、隠岐の島に流される | ||
| 後醍醐天皇 | ごだいご | 南朝 | 鎌倉幕府を滅ぼし、建武の新政を行う | 楠木正成 |
| 光明天皇 | こうみょう | 北朝 | 足利尊氏 | |
|
(徳川政権) |
||||
| 孝明天皇 | こうめい | 妹は和宮 | 和宮は徳川14代将軍の妻 | |
| 明治天皇 | めいじ | 一世一元の制 | ||
上皇(じょうこう)とは、退位した天皇のこと。
法皇(ほうおう)とは、出家した上皇のこと。
重祚(ちょうそ)とは退位した天皇が再び即位することで、中学歴史の範囲では孝謙天皇が重祚して称徳天皇となったことを覚えておけば十分。
中学歴史での天皇の位置づけ
天皇は古代から現代までずっと続いていますが、「中学歴史」という枠組みで見ると、登場する時期は限られています。まずは古代から平安時代の初め(桓武天皇)まで。
天皇中心の国づくり
ここでは倭(日本)という国づくりをするうえで天皇が中心的な役割を果たしていました。古事記、日本書紀の編纂を命じた天武天皇や仏教で国を治めようとした聖武天皇などです。
平安時代に入り摂関政治が全盛期になると天皇は中学歴史上は「お休み」。
摂関政治からの復権(院政)
そこで、摂関政治から天皇中心の政治へ再び戻そうとしたのが、後三条天皇から後白河天皇あたり。白河法皇による院政が有名です。
ところが、平氏、源氏による武士による政権が誕生します。
ここで、また天皇は「お休み」。
武士政権への反発
武士政権のときに天皇中心の政治を復活させようとしたのが後鳥羽上皇と後醍醐天皇で、後鳥羽上皇は失敗(承久の乱)。後醍醐天皇は一時的な成功(建武の新政)を収めました。
こうした流れの中で覚えておくと覚えやすいです。
参考にしてみてください。
天皇について一問一答形式でチェック
中学歴史の問題で●●天皇が答えとなる問題の一問一答をつくりました。
下記ページからチェックしてみて下さい。
こんな問題(↓)になっています(一部のみ掲載)。
| 【問題】 | 【解答】 |
|---|---|
| 倭の五王の武にあたるとされている天皇は? | 雄略天皇 |
| 庚午年籍(初の全国的な戸籍)を制定した天皇は? | 天智天皇 |
| 仏教によって国を治めようと国分寺・国分尼寺を建てた天皇は? | 聖武天皇 |
| 荘園の記録所を設けるなど摂関政治からの脱却を図った天皇は? | 後三条天皇 |
| 南朝の後醍醐天皇に対し、足利尊氏は北朝に( )天皇をたてた | 光明天皇 |