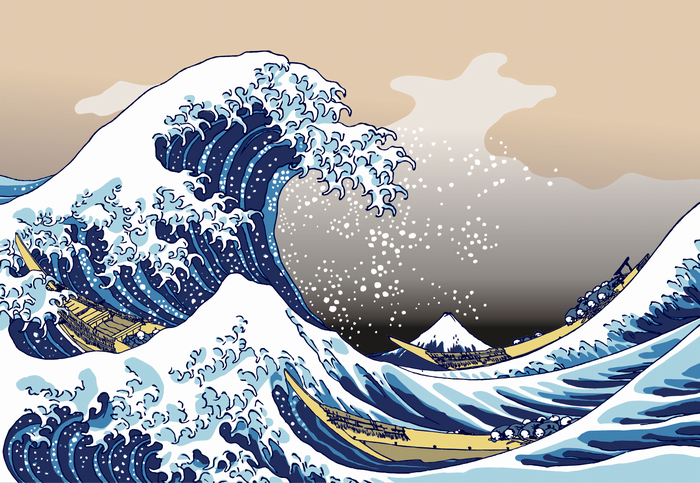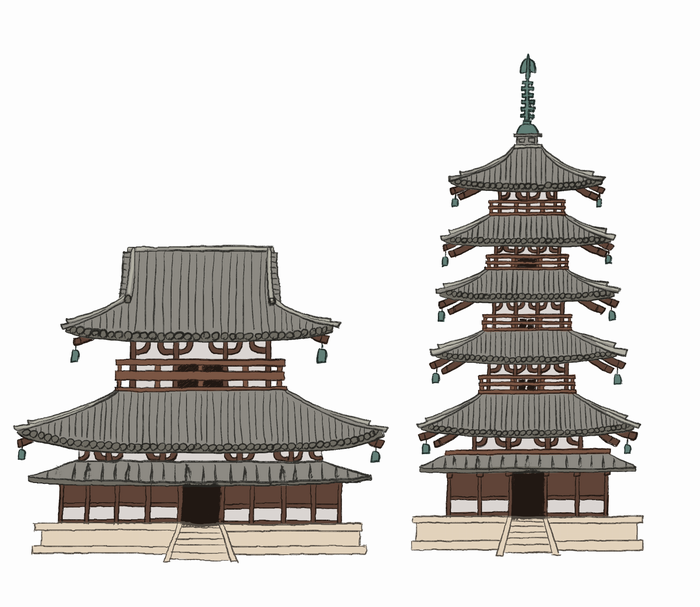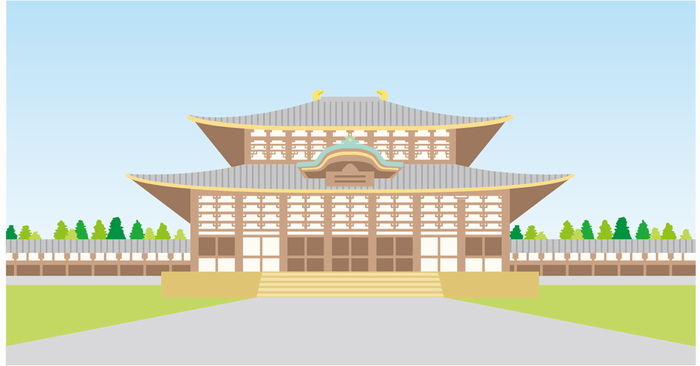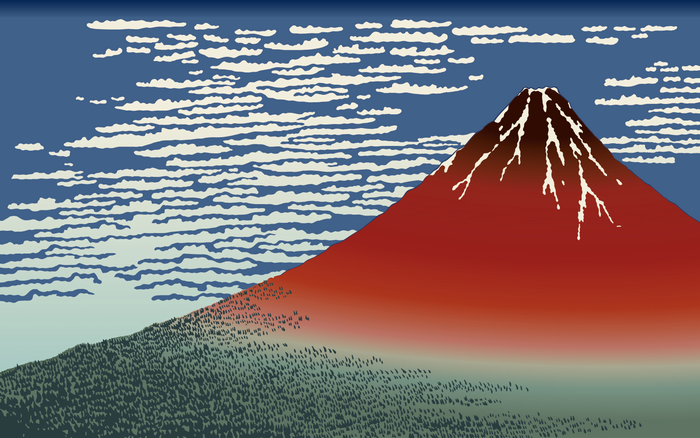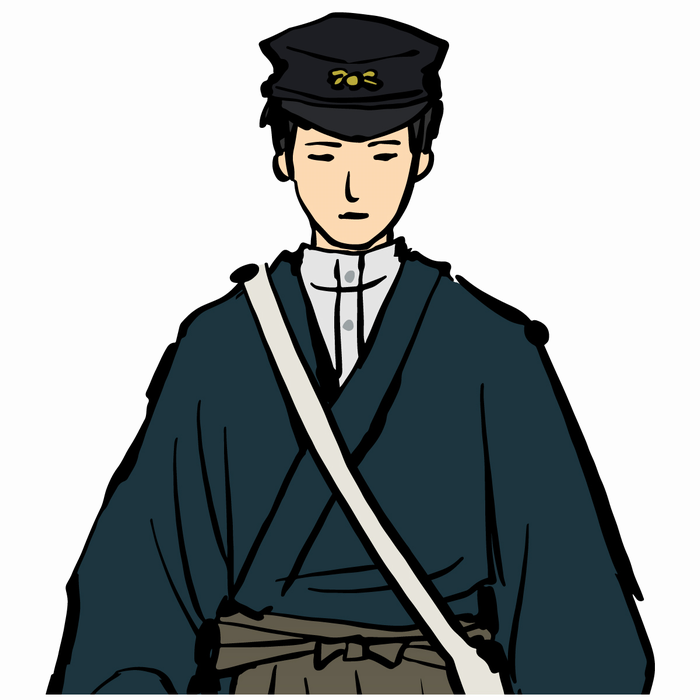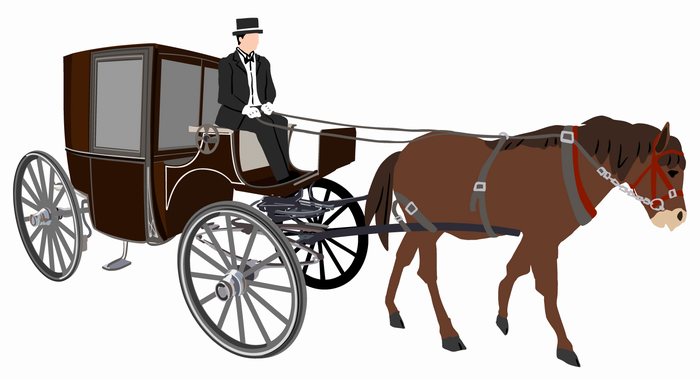元禄文化の特徴は「上方中心」
中学の歴史で習う江戸時代の文化は2つ。元禄文化と化政文化です。
今回は元禄文化についての特徴とポイントをまとめています。
元禄文化の特徴
元禄文化は、江戸時代の17世紀末から18世紀初めにかけて栄えた文化です。
徳川5代将軍綱吉の時代から吉宗が8代将軍になるぐらいまでの期間になります。
大阪や京都などの上方が中心で、町人によって支えられていたことが特徴です。
人形浄瑠璃の近松門左衛門や浮世草子の井原西鶴などが元禄文化を代表する人物。
元禄文化の作品としては、見返り美人図(菱川師宣)や奥の細道(松尾芭蕉)が有名です。
元禄文化の時代背景
元禄年間は1688年から1704年まで。
江戸幕府の将軍は徳川綱吉だった時代です。
忠臣蔵として有名な赤穂事件(赤穂浪士の討ち入りのもとになった事件)があったのが元禄14年3月14日 (旧暦) (1701年4月21日)です。
| 1669年 | シャクシャインの戦い |
|---|---|
| 1685年 | 生類憐みの令 |
| 1709年 | 新井白石の政治(〜1716年) |
| 1716年 | 享保の改革 |
- 上方文化
- 町人中心
- 社会をありのままに描く
仏教の影響を受けた文化の場合は来世のことを取り扱ったものが多くなりますが、元禄文化は現世をありのままに描いています。
現世(この世)のことを浮世(うきよ)ともいいます。
町人の暮らしを生き生き描いた浮世草子や義理と人情の板挟みになる男女を描いた人形浄瑠璃などがその代表となっています。
元禄文化の代表的作品
| 作品名 | 作者 | 分野 |
|---|---|---|
| 奥の細道 | 松尾芭蕉 | 俳諧 |
| 野ざらし紀行 | 松尾芭蕉 | 紀行文 |
| 見返り美人図 | 菱川師宣 | 浮世絵 |
| 二条城障壁画 | 狩野探幽 | 障壁画 |
| 風神雷神図屏風 | 俵屋宗達 | 装飾画 |
| 紅白梅図 | 尾形光琳 | 装飾画 |
| 源氏物語図屏風(げんじものがたりずびょうぶ) | 土佐光起 | 装飾画 |
| 燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ) | 尾形光琳 | 装飾画 |
| 八橋蒔絵螺鈿硯箱(やつはしまきえらでんすずりばこ) | 尾形光琳 | 美術品 |
| 日本永代蔵(にほんえいたいぐら) | 井原西鶴 | 浮世草子 |
| 好色一代男(こうしょくいちだいおとこ) | 井原西鶴 | 浮世草子 |
| 世間胸算用(せけんむねさんよう) | 井原西鶴 | 浮世草子 |
| 曽根崎心中(そねざきしんじゅう) | 近松門左衛門 | 人形浄瑠璃 |
| 国性爺合戦(こくせんやかっせん) | 近松門左衛門 | 人形浄瑠璃 |
| 心中天網島(しんじゅう てんの あみじま) | 近松門左衛門 | 人形浄瑠璃 |
| 冥途の飛脚(めいどのひきゃく) | 近松門左衛門 | 人形浄瑠璃 |
浮世草子というのは当時の小説の形態のことで、町人物、武家物、好色物などのジャンルがあります。
曽根崎心中は実際に起きた事件を題材としたもので「世話物」と呼ばれます。
覚えておきたい元禄文化を代表する人物3名
松尾芭蕉(まつお ばしょう)
俳句の形式や表現を大きく発展させた人物。「古池や 蛙飛びこむ 水の音」「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」などの俳句が有名。「奥の細道」という紀行文は、俳句と文章が一体となった傑作として今も多くの人に読まれています。
井原西鶴(いはら さいかく)
「浮世草子」と呼ばれるジャンルを確立した作家。武士だけでなく、商人や庶民の生活、彼らの欲望や喜び、悲しみなどをリアルに、そして面白く描いたことで人気があった。「世間胸算用(せけんむねさんよう)」「好色一代男(こうしょくいちだいおとこ)」などの作品が有名。
近松門左衛門(ちかまつ もんざえもん)
人形浄瑠璃や歌舞伎の脚本を書いた人物。実際に起きた心中事件を題材にした作品などが当時の人々の共感を呼び、日本の演劇の発展に大きな影響を与えました。「国姓爺合戦(こくせんやかっせん)」「曽根崎心中(そねざきしんじゅう)」などの作品が有名。
関西弁で解説!元禄文化ってなんやねん?
元禄文化ていうのはな、江戸時代の中頃、だいたい1688年から1704年ぐらいの時期に栄えた文化のことや。この頃はな、世の中がめっちゃ平和になって、経済もどんどん発展していったんや。せやから、今まであんまりお金持ってへんかった町人たちが、めっちゃ力を持つようになって、自分たちの文化を作り上げていったんやで。
特徴は「町人」と「娯楽」や!
この時代の文化の特徴は、なんといっても町人が主役やったってことや。武士のお堅い文化と違て、もっと庶民的で、生活を楽しむためのもんがようけ出てきたんや。
ざっくり言うたら、「ちょっと派手で、おもろいもん」ってイメージやな。
代表的なもんを紹介するで!
この人はな、当時のお金持ちや色んな町人の暮らしを、めっちゃリアルにおもしろおかしく書いたんや。「好色一代男(こうしょくいちだいおとこ)」とか「日本永代蔵(にっぽんえいたいぐら)」とか、聞いたことあるかもしれへんな。彼の作品は、当時の大阪の人々の生活をよう表しとるんやで。
「古池や 蛙飛び込む 水の音」って句、知ってるやろ? あれ書いたのがこの人や。俳句っていう、五・七・五の短い詩をめっちゃ広めた人なんや。この人の俳句は、なんかこう、じっくり考えさせられるような深みがあるのが特徴やな。
これは当時の大人気なポスターや雑誌の表紙みたいなもんや。役者さんとか、美人さんとか、旅行の風景なんかをカラフルに描いた絵のことやで。菱川師宣(ひしかわもろのぶ)っていう人が、浮世絵の基礎を作ったんや。
人形を操って物語を演じる芝居のことや。太夫(たゆう)さんが語って、三味線が音を奏でて、人形が動くんや。今でいうと、めっちゃリアルな人形劇みたいなもんやな。近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)っていう人が、めっちゃええ脚本を書いたから、さらに人気になったんや。
これはもう有名やな! 派手な化粧して、ど迫力の演技をするお芝居のことや。
元禄時代に、役者さんがどんどんスターになって、めっちゃ盛り上がったんや。
元禄文化をまとめるとな
せやから、元禄文化っていうのは、町人が主役になって、お金と時間を使って楽しむための文化が花開いた時代ってわけや。派手で、おもろくて、生き生きしとるのが特徴やな。
江戸時代の文化に関する試験対策ページ
元禄文化と化政文化のちがい
江戸時代の文化として紛らわしい元禄文化と化政文化の違いを一問一答形式で確認できるようにしました。どっちが元禄?どっちが化政?かをチェックしてみてください。
| 【問題】どっちが元禄文化? | 【解答】元禄文化 |
|---|---|
| 17世紀末〜18世紀初め or 19世紀初め | 17世紀末〜18世紀初め |
| 将軍綱吉の時代 or 将軍家斉の時代 | 将軍綱吉の時代 |
| 享保の改革より前 or 寛政の改革より後 | 享保の改革より前 |
中学歴史・江戸時代の文化に関する一問一答
| 問題 | 解答 | 覚えておきたいポイント |
|---|---|---|
| 江戸時代に上方を中心に発達した町人文化は? | 元禄文化 | 元禄文化は上方中心、化政文化は江戸中心。どちらも町人文化 |
| 江戸幕府により奨励された「上下関係を重んじる」学問は? | 朱子学 | 「寛政異学の禁」では朱子学以外の学問が禁止された |
| 松尾芭蕉による紀行文は? | 奥の細道 | 俳諧を文学として大成させたのが松尾芭蕉 |
| 人形浄瑠璃の脚本「曽根崎心中」を書いた人物は? | 近松門左衛門 | 近松門左衛門は、義理と人情の世界に生きる男女の悲劇をテーマにしている |
| 杉田玄白らが翻訳した人体解剖書は? | 解体新書 | オランダ語訳の「ターヘル・アナトミア」を日本語に翻訳したのが解体新書 |