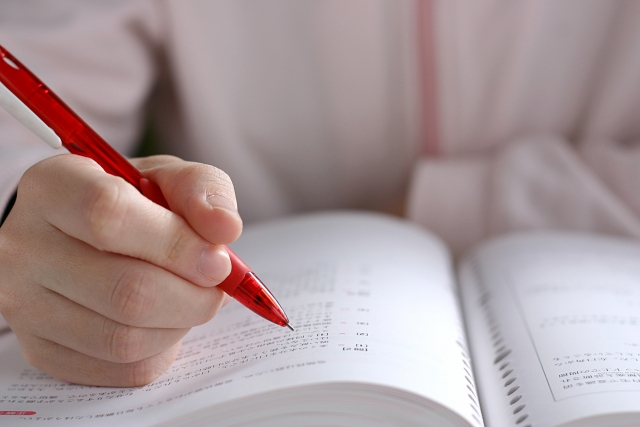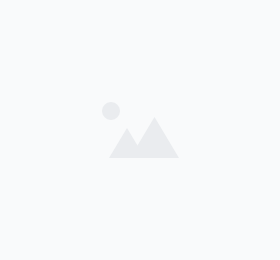中学歴史をまとめて学ぶ(年表からネット問題集まで)

中学歴史の定期テスト対策(建武の新政、足利義満)
「建武の新政」が答えとなる中学歴史の定期テストレベルの問題
- 鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇が行った政治を何と呼ぶか?
- 後醍醐天皇が行った公家を中心とした政治を何と呼ぶか?
- 武士の反感を買い足利尊氏の挙兵により2年ほどで終わった政治を何と呼ぶか?
楠木正成や足利尊氏の力を借りて鎌倉幕府を滅ぼした後醍醐天皇が行った政治が建武の新政です。(建武とは年号のこと。)
建武の新政で後醍醐天皇は公家を重視したために、武士の不満が固まります。その後、足利尊氏の挙兵により、後醍醐天皇は吉野(奈良)に逃れ、建武の新政は終わりました。
関連知識の整理(南朝と北朝)
足利尊氏に追われ吉野(奈良)に逃れた後醍醐天皇が開いたのが南朝。
足利尊氏が京都に開いた北朝とは60年間対立することとなります。
| 南朝 | 北朝 |
|---|---|
| 吉野(奈良) | 京都 |
| 後醍醐天皇が立てた | 足利尊氏が立てた |
南北朝の対立は約60年間続き、3代将軍足利義満のときに合一します。
「足利義満」が答えとなる中学歴史の定期テストレベルの問題
- 足利尊氏の孫で室町幕府第3代将軍は?
- 京都の北山に金閣寺を建てた人物は?
- 明と国交を開き、日明貿易を始めた人物は?
- 対立していた南北朝の合一を実現した人物は?
- 京都の室町に「花の御所」を作り、ここで政治を行った人物は?
足利義満に関する中学歴史レベルの年表
| 西暦 | 足利義満に関する出来事 | その他の出来事 |
|---|---|---|
| 1358年 | 誕生 | |
| 1387年 | 室町に幕府を移す | |
| 1392年 | 南北朝の合一 | |
| 1394年 | 太政大臣となる | |
| 1397年 | 金閣寺建立 | |
| 1404年 | 日明貿易が始まる | |
| 1408年 | 死去 |
室町幕府を開いたのは足利尊氏ですが、幕府の体制を固めたのは3代将軍足利義満。
室町時代と呼ばれるようになったのも義満が京都の室町で政治を行ったからです。また、室町文化を代表する金閣寺を建てたことも忘れてはなりません。
答えが「足利義満」と勘違いしそうな問題
太政大臣でもあり、日宋貿易に力を入れた人物は?
→ 【正解】平清盛。
「太政大臣であること」「中国との貿易に力を入れたこと」は、足利義満と平清盛は同じですが、足利義満は日明貿易、平清盛は日宋貿易です。